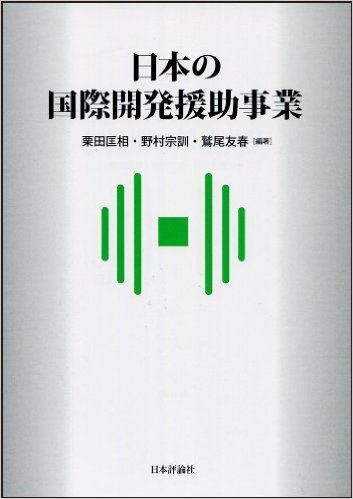伊藤 公一朗 『データ分析の力 因果関係に迫る思考法』
最近、仕事の中でデータを集めたり分析したりすることが多かったので、書店で目に入ったときに思わず購入。平易でわかりやすく、事例も豊富な良書。著者のご年齢を見てびっくり、当方とあまり変わらない。この分野の最先端と全体像の両方を徹底的に理解されているからこそ、こうした本が書けるのだと思う。大きく刺激を受けた。
さて、本書でまず紹介されるのはランダム化比較実験(RCT)の手法。対象者を「ランダムに」振り分け、介入するグループと介入しないグループの結果を比較することで、その介入の効果を測ることができる。要素間の因果関係(相関関係ではない)を証明するためにはこの上ない強力なツールだが、実施には一定のコストがかかる。この手法の適用範囲は極めて広範囲。オバマの大統領選の資金集めでも、どのようなウェブデザインが最も効果的かがRCTを使って検証されていたという。以前紹介したバナジーとデュフロの著書も、RCTにより導かれた開発経済学の知見をまとめたもの。
このRCTが適用できない場合に、一定の自然条件を利用して同様の実験状況を作り出す手法(「境界線」を介入有無とみなすRDデザイン、「階段状の変化」を使う集積分析、「複数期間のデータ」を使うパネルデータ分析)が紹介される。とくにRDデザインの章で、医療費の自己負担額が変わる70歳を境にして受療率が変わることを厚労省「患者統計」のデータ分析で示した先行研究を紹介するくだりは、最近たまたま同統計のデータを使って仕事をしていたこともあり、とても興味深く読んだ。
計量経済学の世界では更に多様な方法が研究されているようだが、本書で紹介されるのはここまで。それでも、データ分析の威力と注意点を当方のような一般人が理解するための入り口としては十分。更なる勉強のための参考図書も巻末に付されている。読後には、「これとあれの因果関係を証明できないか」「この因果関係が言えたら面白いのではないか」等々、以前とは違う新しいものの見方が出来るようになる。
このRCTが適用できない場合に、一定の自然条件を利用して同様の実験状況を作り出す手法(「境界線」を介入有無とみなすRDデザイン、「階段状の変化」を使う集積分析、「複数期間のデータ」を使うパネルデータ分析)が紹介される。とくにRDデザインの章で、医療費の自己負担額が変わる70歳を境にして受療率が変わることを厚労省「患者統計」のデータ分析で示した先行研究を紹介するくだりは、最近たまたま同統計のデータを使って仕事をしていたこともあり、とても興味深く読んだ。
計量経済学の世界では更に多様な方法が研究されているようだが、本書で紹介されるのはここまで。それでも、データ分析の威力と注意点を当方のような一般人が理解するための入り口としては十分。更なる勉強のための参考図書も巻末に付されている。読後には、「これとあれの因果関係を証明できないか」「この因果関係が言えたら面白いのではないか」等々、以前とは違う新しいものの見方が出来るようになる。
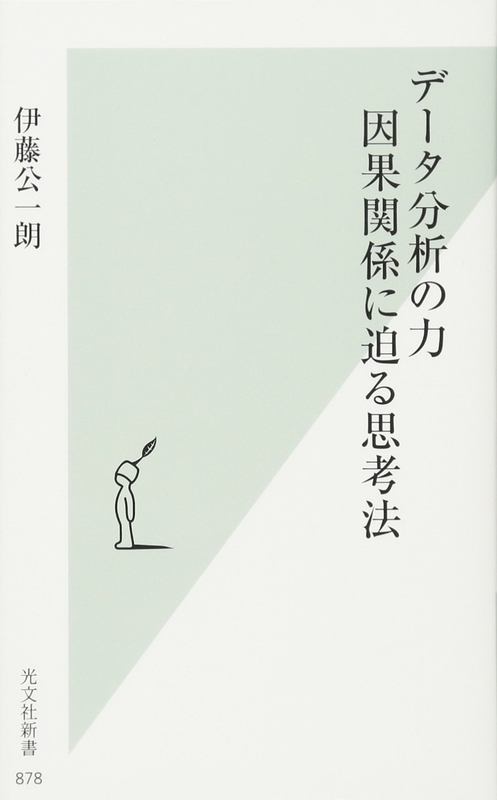
(2017年、光文社新書)
深田 祐介 『神鷲商人』
巻末の対談集によれば、著者の深田氏の幼友達が商社でインドネシア賠償に深く関わっていたことをきっかけに、本書の執筆がスタートしたという。インドネシア賠償で活躍した複数の日本商社や、デヴィ夫人本人にも取材を重ねた結果、当時の様子がリアルに描かれている。本書で登場する商社のひとつは、以前紹介した日本賠償の専門書にも登場する、特に中古船の調達で大きな利益を得たといわれる木下商店(後に三井物産に吸収合併)である。
前掲の専門書は、対インドネシア賠償資金が外資系オフィスビルや高級デパート、ホテルにまで使われたことを、批判的に紹介していた。一方、この小説の中では、スカルノもそれなりの理由を持ってこれらの開発を主導したことが示唆されている。(いわく、ホテルは、当時、経済発展のために外資を導入しようにも外国人がまともに泊まれるホテルがなかったため。デパートは、国内で流通する諸商品の価格をベンチマークするため。)
前掲の専門書は、対インドネシア賠償資金が外資系オフィスビルや高級デパート、ホテルにまで使われたことを、批判的に紹介していた。一方、この小説の中では、スカルノもそれなりの理由を持ってこれらの開発を主導したことが示唆されている。(いわく、ホテルは、当時、経済発展のために外資を導入しようにも外国人がまともに泊まれるホテルがなかったため。デパートは、国内で流通する諸商品の価格をベンチマークするため。)
賠償資金を原資とした調達において、日尼の政界へのリベートがどのように編み出されていたのか、その描写も生々しくて面白い。商社が落札した金額の数パーセントが、その落札を後押しした日本の政治家と当時のスカルノの懐に収まる仕組み。当然、こうしたリベートも上乗せした金額で契約される訳なので、事業費の総額は膨らむ。日本がインドネシアにもたらした惨禍、文字通りインドネシア国民の血で贖われた資金が、このような仕組みを通って本来とは異なる目的で使われていたことには、何とも言えない気分にさせられる。
また、こうした賠償をめぐる日本商社の受注競争には、複数の女性達が巻き込まれた。スカルノが東京のナイトクラブで見初めた直美(デヴィ夫人がモデル)は、商社の手引きで、ジャカルタの宮殿に文字通り送り込まれる。しかし、それと引き換えに商社から受け取った資金が遠因となって、東京に残してきた家族は崩壊する。ジャカルタでの生活は孤独であり、自分が知らない間にスカルノが新しい妻を娶っていたことを知って打ちのめされ、睡眠薬を飲んで服毒自殺を図る。もう一人の主人公である商社駐在員の冨永は、こうした直美の辛さを知って同情するが、冷徹な上司の小笠原は直美を商売道具の一つとしてしか見ず、嫌気が差した冨永は退社して独立する。日本の戦後の対アジア関係は、かくも生々しい人々のドラマによって始まったとも言える。
また、こうした賠償をめぐる日本商社の受注競争には、複数の女性達が巻き込まれた。スカルノが東京のナイトクラブで見初めた直美(デヴィ夫人がモデル)は、商社の手引きで、ジャカルタの宮殿に文字通り送り込まれる。しかし、それと引き換えに商社から受け取った資金が遠因となって、東京に残してきた家族は崩壊する。ジャカルタでの生活は孤独であり、自分が知らない間にスカルノが新しい妻を娶っていたことを知って打ちのめされ、睡眠薬を飲んで服毒自殺を図る。もう一人の主人公である商社駐在員の冨永は、こうした直美の辛さを知って同情するが、冷徹な上司の小笠原は直美を商売道具の一つとしてしか見ず、嫌気が差した冨永は退社して独立する。日本の戦後の対アジア関係は、かくも生々しい人々のドラマによって始まったとも言える。
(2001年、文春文庫、上・下巻)
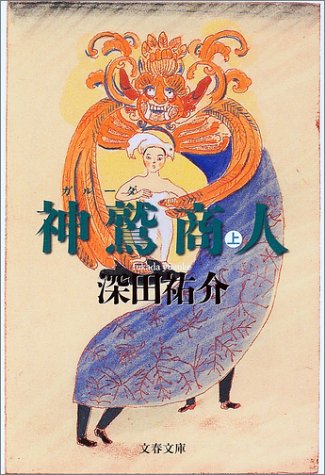
浅田 次郎 『蒼穹の昴』
学生時代に一度読んだが、懐かしくなって再度手にとってみた。浅田氏は巷で「平成の泣かせ屋」と呼ばれているらしいが、たしかに名場面の数々でホロリとさせられる。
主人公は、直隷省静海県の貧しい糞拾いの少年・春児と、幼馴染の兄貴分である地主の次男・梁文秀。物語は、文秀が科挙のために春児を連れて上京するところから始まる。泊まり込みで古典や詩歌、政策を論ずる科挙の詳細な描写は、それだけで興味深い。当初は落第すると思われた文秀は、隣室の老人に礼をもって接したことから、夢か現か、天命を身につけ、渾身の解答をもって状元(第一位)に処せられる。以後、順調に出世するが、西太后と取り巻きの奸臣の政争に翻弄される清朝政府の内情を見て、その改革を志すようになる。
いっぽう春児は、宦官になるために一物を切り取られる現場を見て一度は気持ちが萎えるも、「やがて中華の財物全てを手にするであろう」という占い師の言葉を信じ、自ら浄身して再度都に上る。そこで、城を追われた元宦官に見初められ、英才教育を受ける。満を辞して城に入った春児は、こちらも順調に出世し、やがて西太后から直接寵愛を受けるまでになる。
清朝の中枢に入った二人だが、皇帝の下で中国の「明治維新」をなさんとする変法派の官僚と、西太后に仕える(そもそも官僚に近づくことを許されない)宦官の道はなかなか交差しない。変法派のクーデターが失敗に終わった後、潔く自死しようとする文秀の前で、春児は占い師の言葉が偽りであることを知っていたと告白する。運命は、頑張れば変えられる。だから文秀も生きてくれ、と懇願する。
印象的な登場人物が多いが、中でも主人公の春児の一挙手一投足は、どうしても気になる。純粋でいじらしい、しかし過酷な運命に抗って自ら道を切り開いていく様は、どうしても応援したくなる。私利私欲のない純粋な人柄で、溜まった私財は、孤児院への寄付や下っ端の宦官の一物を買い戻すのに使う。謀略に巻き込まれて殺された老宦官を弔うシーン、悪役の大総官と副総官と対峙するが、周りの宦官たちは体を張って春児を守る:
「こいつは老祖宗に引き立てられたばかりじゃなく、みんなに推されて出世した初めての太監だ・・・・春児はな、殴られっぱなしのわしらの、夢だったんだ・・・神様ってのは、こういうもんだ。決して拝んだり頼ったりするもんじゃねえ。いつも貧乏な人間のそばにいて、いてくれるだけで生きる望みをつないでくれる、ありがてえ、かわいいものだ。春児を殺すならまずわしを殺せ。そうすりゃたぶん極楽に行ける。」
朽ち果て野垂れ死ぬのみだった天命を、自らの徳と知恵で覆した春児。辛いことがあっても前向きに生きていこう、そうすればきっと道は開ける、と励まされるような気持ちになる。
主人公は、直隷省静海県の貧しい糞拾いの少年・春児と、幼馴染の兄貴分である地主の次男・梁文秀。物語は、文秀が科挙のために春児を連れて上京するところから始まる。泊まり込みで古典や詩歌、政策を論ずる科挙の詳細な描写は、それだけで興味深い。当初は落第すると思われた文秀は、隣室の老人に礼をもって接したことから、夢か現か、天命を身につけ、渾身の解答をもって状元(第一位)に処せられる。以後、順調に出世するが、西太后と取り巻きの奸臣の政争に翻弄される清朝政府の内情を見て、その改革を志すようになる。
いっぽう春児は、宦官になるために一物を切り取られる現場を見て一度は気持ちが萎えるも、「やがて中華の財物全てを手にするであろう」という占い師の言葉を信じ、自ら浄身して再度都に上る。そこで、城を追われた元宦官に見初められ、英才教育を受ける。満を辞して城に入った春児は、こちらも順調に出世し、やがて西太后から直接寵愛を受けるまでになる。
清朝の中枢に入った二人だが、皇帝の下で中国の「明治維新」をなさんとする変法派の官僚と、西太后に仕える(そもそも官僚に近づくことを許されない)宦官の道はなかなか交差しない。変法派のクーデターが失敗に終わった後、潔く自死しようとする文秀の前で、春児は占い師の言葉が偽りであることを知っていたと告白する。運命は、頑張れば変えられる。だから文秀も生きてくれ、と懇願する。
印象的な登場人物が多いが、中でも主人公の春児の一挙手一投足は、どうしても気になる。純粋でいじらしい、しかし過酷な運命に抗って自ら道を切り開いていく様は、どうしても応援したくなる。私利私欲のない純粋な人柄で、溜まった私財は、孤児院への寄付や下っ端の宦官の一物を買い戻すのに使う。謀略に巻き込まれて殺された老宦官を弔うシーン、悪役の大総官と副総官と対峙するが、周りの宦官たちは体を張って春児を守る:
「こいつは老祖宗に引き立てられたばかりじゃなく、みんなに推されて出世した初めての太監だ・・・・春児はな、殴られっぱなしのわしらの、夢だったんだ・・・神様ってのは、こういうもんだ。決して拝んだり頼ったりするもんじゃねえ。いつも貧乏な人間のそばにいて、いてくれるだけで生きる望みをつないでくれる、ありがてえ、かわいいものだ。春児を殺すならまずわしを殺せ。そうすりゃたぶん極楽に行ける。」
朽ち果て野垂れ死ぬのみだった天命を、自らの徳と知恵で覆した春児。辛いことがあっても前向きに生きていこう、そうすればきっと道は開ける、と励まされるような気持ちになる。
(2004年、講談社文庫、全4巻)

濱田 健司 『農福連携の「里マチ」づくり』
JA共済総合研究所の濱田氏が、「農福連携」の仕組みと事例を解説した本。
とある地方部の自治体の方から「農福連携」という言葉を聞いて、調べてみようと思って手にとったのがこの本。写真や図表も多数入っていて、分かりやすい構成になっている。
「農福連携」とは、その名の通り、「農」(農生業)と「福」(福祉。障がい者の就労)をつなぐ取り組み。日本の農業は、担い手不足にあえいでいる。働く意思のある障がい者のうち、就労できていない人は6割弱に上る。障がい者向けの園芸療法や農作業体験など、農業と福祉の緩やかな連携はこれまでもあった。これを超えて、障がい者に本格的に就農させ、実際に収益を上げようという試みである。「障がい者に農業はできない」という声もあったが、近年は、各地で事例が生まれているという。そして、そこで新たな価値が生まれることにより、高齢化や人口減少で停滞したまちも活性化できる可能性があるという。
とある地方部の自治体の方から「農福連携」という言葉を聞いて、調べてみようと思って手にとったのがこの本。写真や図表も多数入っていて、分かりやすい構成になっている。
「農福連携」とは、その名の通り、「農」(農生業)と「福」(福祉。障がい者の就労)をつなぐ取り組み。日本の農業は、担い手不足にあえいでいる。働く意思のある障がい者のうち、就労できていない人は6割弱に上る。障がい者向けの園芸療法や農作業体験など、農業と福祉の緩やかな連携はこれまでもあった。これを超えて、障がい者に本格的に就農させ、実際に収益を上げようという試みである。「障がい者に農業はできない」という声もあったが、近年は、各地で事例が生まれているという。そして、そこで新たな価値が生まれることにより、高齢化や人口減少で停滞したまちも活性化できる可能性があるという。
本書では、この様々な事例が紹介される。最も印象に残ったのは、広島県庄原市の社会福祉法人・優輝福祉会のとりくみ。高齢者と障がい者の施設、保育園を経営。敷地には、パン屋とレストランもなっている。近隣の農家から野菜を調達して、施設の食材として使う。スタッフと障がい者が組になって、農家の集荷を手伝う。捨てるはずだった自家栽培の野菜は、施設のレストランやパンやで仕える地域通貨。職員300人、障がい者150人、高齢者500人、年間の食材費だけでも一億数千万円かかっていたが、いまや食材の40%近くをこうして地元で調達する。また、住宅団地の開発にも参画して、人を集めるための特色ある団地にするために、敷地内の源泉を使って足湯を作る。お湯を温めるための光熱費は、里山のバイオマス。手間がかかる作業だが、「手間がかかるから、障がい者の仕事が生まれる」。読了後に気づいたが、この庄原市の事例は、前回投稿した『里山資本主義』でも紹介されていた。
鹿児島県大隈町の社会福祉法人白鳩会は、40年も前から障がい者と健常者が一緒になって農業を行い、今では農地を東京ドーム10個分にまで広げている。障がい者が自立した生活を送るため、療育目的ではない、稼ぐための農業を、企業体として行う:
「南大隈町で自立した生活を送るには、最低月11万円必要です。障がい者年金の7万円を引いたら、4万円。じゃあ4万円を達成するには、どうするか。まず、職員は給料を20万円もらおうじゃないか。この20万円は、国から入ってくる。もし、この職員が自分の給料、20万円を農業で稼ぐ、という意識で働いたとしたら、5人の障がい者に4万円を支払うことができる。」
「職員と障がい者がチームとなって、農業で、いっしょに月20万円の収益を目指していく。すると、そこには教えたり、教えられたりする絶対的な関係はなくなる。」
かつては、障がい者を使って儲けようとしているのではないかと見られ、行政からも目を付けられていた。白鳩会の取り組みが評価されるようになったのは、障がい者も自らの努力によって自立できるという考え方が広まった、つい近年になってからのことだという。
「南大隈町で自立した生活を送るには、最低月11万円必要です。障がい者年金の7万円を引いたら、4万円。じゃあ4万円を達成するには、どうするか。まず、職員は給料を20万円もらおうじゃないか。この20万円は、国から入ってくる。もし、この職員が自分の給料、20万円を農業で稼ぐ、という意識で働いたとしたら、5人の障がい者に4万円を支払うことができる。」
「職員と障がい者がチームとなって、農業で、いっしょに月20万円の収益を目指していく。すると、そこには教えたり、教えられたりする絶対的な関係はなくなる。」
かつては、障がい者を使って儲けようとしているのではないかと見られ、行政からも目を付けられていた。白鳩会の取り組みが評価されるようになったのは、障がい者も自らの努力によって自立できるという考え方が広まった、つい近年になってからのことだという。
本書で紹介されている事例は、いまでは成功事例のように見えるが、そこに至るまでには言葉では語りつくせないご苦労があったに違いない。決して簡単なことではないと思うが、こうした取組みに労力を傾けられてきた関係者の方々には、純粋に尊敬の念を抱かざるを得ない。『里山資本主義』の考え方にも通じるかもしれないが、こうした取り組みがもっと広がれば、たとえGDPには直接あらわれないにしても、もっと居心地の良い、生き生きとした社会になっていくのではないかなと考えさせられた。
(2015年、鹿島出版会)
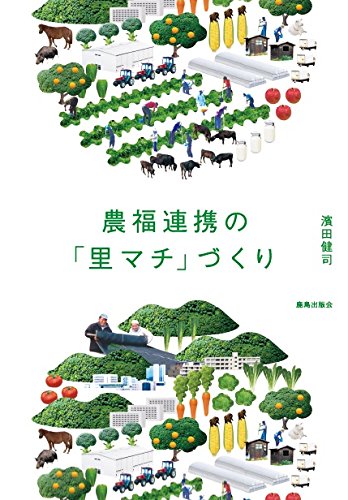
藻谷 浩介、NHK広島取材班 『里山資本主義 日本経済は「安心の原理」で動く』
「里山資本主義」は、NHK広島取材班が編み出した造語。取材班の井上氏は、以前本ブログでも紹介した「マネー資本主義」の番組を手がけており、金融が実体経済を凌駕する現代のアンチテーゼを模索する中、中国山地での取材を通じてこの言葉を思いついたという。本書の解説役である藻谷氏によれば:
「お金の循環がすべてを決する前提で構築された「マネー資本主義」の経済システムの横に、こっそりと、お金に依存しないサブシステムを再構築しておこうという考え方だ。お金が乏しくなっても水と食料と燃料が手に入り続ける仕組み、いわば安心安全のネットワークを、予め用意しておこうという実践だ。(中略)森や人間関係といったお金で買えない資産に、最新のテクノロジーを加えて活用することで、マネーだけが頼りの暮らしよりも、はるかに安心で安全で底堅い未来が出現するのだ。」
本書では、このコンセプトを裏付ける、様々な事例が紹介される。
岡山県真庭市で実践される、製材過程で出るパレットを使った木質バイオマス発電。広島県庄原市で、エコストーブなど、里山の恵みを最大限に生かしながら暮らす住民の方々。オーストリアでは、林業技術の先端化と教育、政治のリーダーシップにより、木質バイオマスを使ったエネルギーの地域循環を達成しつつある地域がある。また、同国では、木版の集合材CLTが、強度や耐火性に優れていることが証明され、9階建てのビルの建築にまで用いられている。日本でも、CLTの実証実験が始まっている。
自然資源だけではなく、人間関係の回復にも焦点が当てられる。象徴的な事例は、庄原市の福祉施設。過疎が進む地域だが、空き家を利用して施設にする。施設の運営に必要な食材は、近隣のお年寄りが作った半端者の野菜を譲ってもらう。対価として地域通貨を支払い、その通貨は施設のレストランで使われる。レストランは、お年寄りが友人知人と言葉を交わす賑わいの場。併設する保育園で子供と遊ぶこともできる。障害者たちも、野菜の引き取りやレストランの給仕として活躍する。生産者、客、店員が絆を作っていく。
「お金の循環がすべてを決する前提で構築された「マネー資本主義」の経済システムの横に、こっそりと、お金に依存しないサブシステムを再構築しておこうという考え方だ。お金が乏しくなっても水と食料と燃料が手に入り続ける仕組み、いわば安心安全のネットワークを、予め用意しておこうという実践だ。(中略)森や人間関係といったお金で買えない資産に、最新のテクノロジーを加えて活用することで、マネーだけが頼りの暮らしよりも、はるかに安心で安全で底堅い未来が出現するのだ。」
本書では、このコンセプトを裏付ける、様々な事例が紹介される。
岡山県真庭市で実践される、製材過程で出るパレットを使った木質バイオマス発電。広島県庄原市で、エコストーブなど、里山の恵みを最大限に生かしながら暮らす住民の方々。オーストリアでは、林業技術の先端化と教育、政治のリーダーシップにより、木質バイオマスを使ったエネルギーの地域循環を達成しつつある地域がある。また、同国では、木版の集合材CLTが、強度や耐火性に優れていることが証明され、9階建てのビルの建築にまで用いられている。日本でも、CLTの実証実験が始まっている。
自然資源だけではなく、人間関係の回復にも焦点が当てられる。象徴的な事例は、庄原市の福祉施設。過疎が進む地域だが、空き家を利用して施設にする。施設の運営に必要な食材は、近隣のお年寄りが作った半端者の野菜を譲ってもらう。対価として地域通貨を支払い、その通貨は施設のレストランで使われる。レストランは、お年寄りが友人知人と言葉を交わす賑わいの場。併設する保育園で子供と遊ぶこともできる。障害者たちも、野菜の引き取りやレストランの給仕として活躍する。生産者、客、店員が絆を作っていく。
最後のまとめの章で、藻谷氏は「人間の価値は、誰かに『あなたはかけがえのない人だ』と言ってもらえるかどうかで決まる」と書いている。上記の庄原市の事例では、「生産者の生きがいの増加、施設の利用者の健康の増進、結果としていらなくなった食材代や肥料代、それを運ぶはずだった燃料代。いずれも金銭換算できない価値、あるいはGDPにとってはマイナスだが現実には意味のある価値であり、それらが地域内を循環しながら輪を拡大させている」。
この本を読んで、非常に考えさせられることが多かった。金銭換算できない価値の大切さを測ることは難しい。国や世界の経済は、冷徹に、金銭価値の論理で動いていく。それを全て否定することは難しいが、少なくとも自治体や地域のレベルでは、自然資源や人間関係にもっと価値を置く考え方があって良い。直観的には、むしろその方が健全ではないかという気がしている。
この本を読んで、非常に考えさせられることが多かった。金銭換算できない価値の大切さを測ることは難しい。国や世界の経済は、冷徹に、金銭価値の論理で動いていく。それを全て否定することは難しいが、少なくとも自治体や地域のレベルでは、自然資源や人間関係にもっと価値を置く考え方があって良い。直観的には、むしろその方が健全ではないかという気がしている。
(角川新書、2013年)

加藤 洋輝・桜井 駿 『決定版 FinTech 金融革命の全貌』
フィンテックの入門書はこの本以外にもたくさん出ているが、構成が分かりやすそうなだったので手にとってみた。読んだのは少し前だが、備忘録として書き込んでおく。
本書の分類によれば、フィンテックの代表的なサービスは、①融資、②決済、③送金、④投資、⑤情報管理、⑥業務支援、⑦仮想通貨(ビットコイン)。それぞれ代表的なビジネスモデルや提供企業が挙げられている。
①融資は、Lending Club という米国のサービスが存在感を増している。クラウドファンディングの類型「寄付型」「購入型」「投資型」のうち「投資型」に該当。最後に該当するもの。消費者信用スコア以外の、SNSやPFM、EC購買歴などをビッグデータ解析、それをもとに与信ランクを判断するという。比較的信用が高い個人を対象とすることで貸倒れリスクを抑えつつ、投資家にとっては銀行預金や国債よりも魅力的な商品になっており、与信総額はいまや1兆円を超えているという。本書の巻末でも示唆されるように、金融は、仲介者たる金融機関を飛ばして、一対一の取引という原初の姿に戻り始めているのかもしれない。
著者が「突然変異で生まれた飛び地」と位置付けるのが⑦仮想通貨のビットコイン。為替、送金、決済の機能を併せ持つ。ブロックチェーン、P2Pネットワーク、プルーフオブワークという3つの技術・アイデアを組み合わせることで、革新的なアイデアを現実の世に送り出した。
また、フィンテックを支えるのは、5つの要素技術だという:①モバイル端末、②ビッグデータ、③人工知能、④API(複数のプログラムの機能やデータを外部と接続する際の規格・規約)、⑤デザイン。
①融資は、Lending Club という米国のサービスが存在感を増している。クラウドファンディングの類型「寄付型」「購入型」「投資型」のうち「投資型」に該当。最後に該当するもの。消費者信用スコア以外の、SNSやPFM、EC購買歴などをビッグデータ解析、それをもとに与信ランクを判断するという。比較的信用が高い個人を対象とすることで貸倒れリスクを抑えつつ、投資家にとっては銀行預金や国債よりも魅力的な商品になっており、与信総額はいまや1兆円を超えているという。本書の巻末でも示唆されるように、金融は、仲介者たる金融機関を飛ばして、一対一の取引という原初の姿に戻り始めているのかもしれない。
著者が「突然変異で生まれた飛び地」と位置付けるのが⑦仮想通貨のビットコイン。為替、送金、決済の機能を併せ持つ。ブロックチェーン、P2Pネットワーク、プルーフオブワークという3つの技術・アイデアを組み合わせることで、革新的なアイデアを現実の世に送り出した。
また、フィンテックを支えるのは、5つの要素技術だという:①モバイル端末、②ビッグデータ、③人工知能、④API(複数のプログラムの機能やデータを外部と接続する際の規格・規約)、⑤デザイン。
(2016年、東洋経済新報社)
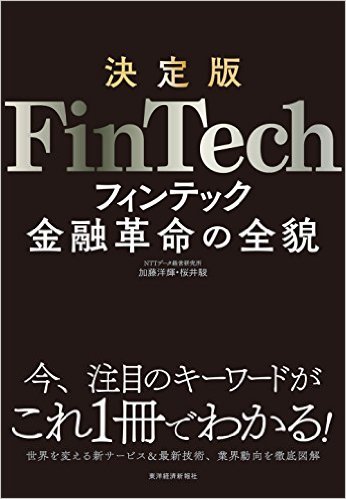
栗田 匡相 ほか 編著 『日本の国際開発援助事業』
1.理論・背景(全体、アジア、アフリカ)、2.ハード・インフラ(エネルギー、水道、道路等)、3.ソフト・インフラ(教育、保険医療等)の3部構成になっている。PPPによるインフラ整備、NGOとの連携、援助協調、インフラ輸出等々、ODAを語る上で欠かせない近年のトレンドをコンパクトに抑えている。ODAについて概観したい学生や一般の方々におすすめ。
個人的に印象に残ったのは、以下の2論考。いずれも総論としては賛同。より具体的な提言に至るには、研究者と実務者の双方が、更に議論を深めていく必要がある。
●アフリカ向けODAの展開(遠藤衛・高橋基樹)
・財政支援が時流となる中、日本は、米国のミレニアム・チャレンジ・アカウントのように独自の財政支援スキームを作ることもなく、従来通りプロジェクト中心の無償資金協力を展開してきた。
・借款を中心とした日本のODAは、アジアの工業化を背景とした経済インフラ整備、産業人材育成のニーズに対応してきた。
・しかし、1970年代までに一定の輸入代替工業化を成功させていたアジアの国々と、そうでないアフリカの国々では、「援助のニーズや受入方に大きな違い」があり、この点を踏まえて「新しい援助のあり方を模索する勇気」が必要。
・財政支援が時流となる中、日本は、米国のミレニアム・チャレンジ・アカウントのように独自の財政支援スキームを作ることもなく、従来通りプロジェクト中心の無償資金協力を展開してきた。
・借款を中心とした日本のODAは、アジアの工業化を背景とした経済インフラ整備、産業人材育成のニーズに対応してきた。
・しかし、1970年代までに一定の輸入代替工業化を成功させていたアジアの国々と、そうでないアフリカの国々では、「援助のニーズや受入方に大きな違い」があり、この点を踏まえて「新しい援助のあり方を模索する勇気」が必要。
●教育分野のODA(關谷武司・芦田明美)
・JICAの技術協力について、プロジェクト期間の短縮や評価の厳格化に伴い、じっくり腰を下ろして「人づくり」するよりも、あたかも「箱物型プロジェクトのように型にはまったシステマティックな人材育成」にならざるを得なくなっている。
・他ドナーには見られない日本の技術協力の特長は、「きめ細やかさ、口先だけではない本当のオーナーシップやパートナシップ尊重」であり、効率化の努力はしつつも、こうした良さを忘れないことが重要。
・JICAの技術協力について、プロジェクト期間の短縮や評価の厳格化に伴い、じっくり腰を下ろして「人づくり」するよりも、あたかも「箱物型プロジェクトのように型にはまったシステマティックな人材育成」にならざるを得なくなっている。
・他ドナーには見られない日本の技術協力の特長は、「きめ細やかさ、口先だけではない本当のオーナーシップやパートナシップ尊重」であり、効率化の努力はしつつも、こうした良さを忘れないことが重要。
(日本評論社、2014年)