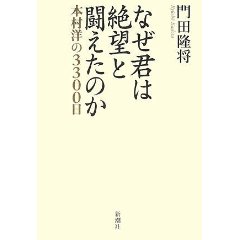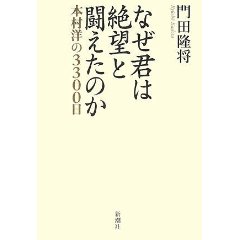門田 隆将 『なぜ君は絶望と闘えたのか 本村洋の3300日』
1999年山口県光市母子殺害事件を、事件直後から今年4月の被告への死刑判決まで、実に9以上にわたって本村洋さんら被害者遺族の戦いを追い続けたジャーナリスト・門田さんによる記録。
本屋で衝動買い、そのまま読み終えてしまいましたが、本を読んで涙したのは久しぶりでした。
23歳で妻を殺害・死後強姦され、生後1歳に満たない娘を殺害された本村さん。2000年地裁での被告への無期懲役判決を受けた直後、「自分の手で犯人を殺す」と述べたあまりにも強烈な記者会見は、今でも覚えています。当時自分はまだ高校生でしたが、もし自分が本村さんの立場であったなら・・・と想像して思わず震えた記憶があります。
事件直後、本村さんが選んだ選択は、「事件を風化させるのではなく、積極的に社会に対し被害者としての立場で発言を行い、事件を社会の目に晒すことで、司法制度や犯罪被害者の置かれている立場の状況の問題点を見出してもらう」こと。残酷に過ぎる犯行内容、当時の司法制度、本村さん自身の年齢-当時たった23歳-を考えれば、どんなにつらい選択だったろうと思います。
本屋で衝動買い、そのまま読み終えてしまいましたが、本を読んで涙したのは久しぶりでした。
23歳で妻を殺害・死後強姦され、生後1歳に満たない娘を殺害された本村さん。2000年地裁での被告への無期懲役判決を受けた直後、「自分の手で犯人を殺す」と述べたあまりにも強烈な記者会見は、今でも覚えています。当時自分はまだ高校生でしたが、もし自分が本村さんの立場であったなら・・・と想像して思わず震えた記憶があります。
事件直後、本村さんが選んだ選択は、「事件を風化させるのではなく、積極的に社会に対し被害者としての立場で発言を行い、事件を社会の目に晒すことで、司法制度や犯罪被害者の置かれている立場の状況の問題点を見出してもらう」こと。残酷に過ぎる犯行内容、当時の司法制度、本村さん自身の年齢-当時たった23歳-を考えれば、どんなにつらい選択だったろうと思います。
それはたった一人の戦いだったのか?
⇒著者の答えは否。事件後ショックに打ちひしがれ辞表を提出した本村さんに対し、職場である新日本製鉄の上司は、「君は、社会人として発言していってくれ。労働も納税もしない人間が社会に訴えても、それはただの負け犬の遠吠えだ。君は社会人たりなさい。」と言った。「全国犯罪被害者の会」のメンバーとの交流と、刑事訴訟法をはじめ日本の司法制度を変えるための活動。また、本村さんの言葉に心動かされ、涙を流し、捜査にまい進し続けた検事たちの執念があった。
それでも死刑制度はあるべきなのか?
それでも死刑制度はあるべきなのか?
⇒本村さんの答えは、あくまで「あるべき」。他事件の死刑囚との交流を通じて「一方で死刑囚も同じ人間」という事実に直面するが、「被害者の命と遺族とのつながりを断ち切る殺害という犯罪はあくまで犯人の命によって贖われるべき」という本村さんの考えは最後まで揺るがなかった。
死刑宣告によって、犯人は真に「死とは何か」という問題に真剣に向き合わざるを得なくなる。事実、死刑判決直後、法廷での荒唐無稽な自己弁護とは打って変わって、被告は著者との面会の中で「被害者の数がたとえ1人でも、その人の遺族とのつながりを思えば、死刑は当然」と述べた。著者によれば、そのとき被告は、真剣に自身の罪と死、そして自身が奪った2つの命の重さについて考えを至らせていた。
死刑宣告によって、犯人は真に「死とは何か」という問題に真剣に向き合わざるを得なくなる。事実、死刑判決直後、法廷での荒唐無稽な自己弁護とは打って変わって、被告は著者との面会の中で「被害者の数がたとえ1人でも、その人の遺族とのつながりを思えば、死刑は当然」と述べた。著者によれば、そのとき被告は、真剣に自身の罪と死、そして自身が奪った2つの命の重さについて考えを至らせていた。
読み終えて、重い読後感が残りました。死刑制度、司法制度、少年法・・・。さまざまな論点は提示されるけれども、やはり一番印象に残るのは本村さんが発する言葉や行動の節々からにじみ出る、絶望や怒り、慟哭といったあまりにもストレートな感情、そして特別な経験をした方ならではの深い重みをもった死生観・人生観。
悲惨な事件の全貌を包み隠さず公に公開し、周囲の人々の助けを借りつつも反論や障害に怯まず戦い続けた本村さんに、心から尊敬の念を表したいと思います。
また、既存の司法慣習を覆した今年4月の死刑判決によって、悲惨な事件の被害者のお二人の魂が、少しでも安らかに浮かばれることを、お祈りします。
悲惨な事件の全貌を包み隠さず公に公開し、周囲の人々の助けを借りつつも反論や障害に怯まず戦い続けた本村さんに、心から尊敬の念を表したいと思います。
また、既存の司法慣習を覆した今年4月の死刑判決によって、悲惨な事件の被害者のお二人の魂が、少しでも安らかに浮かばれることを、お祈りします。
(2008年7月発行、新潮社)